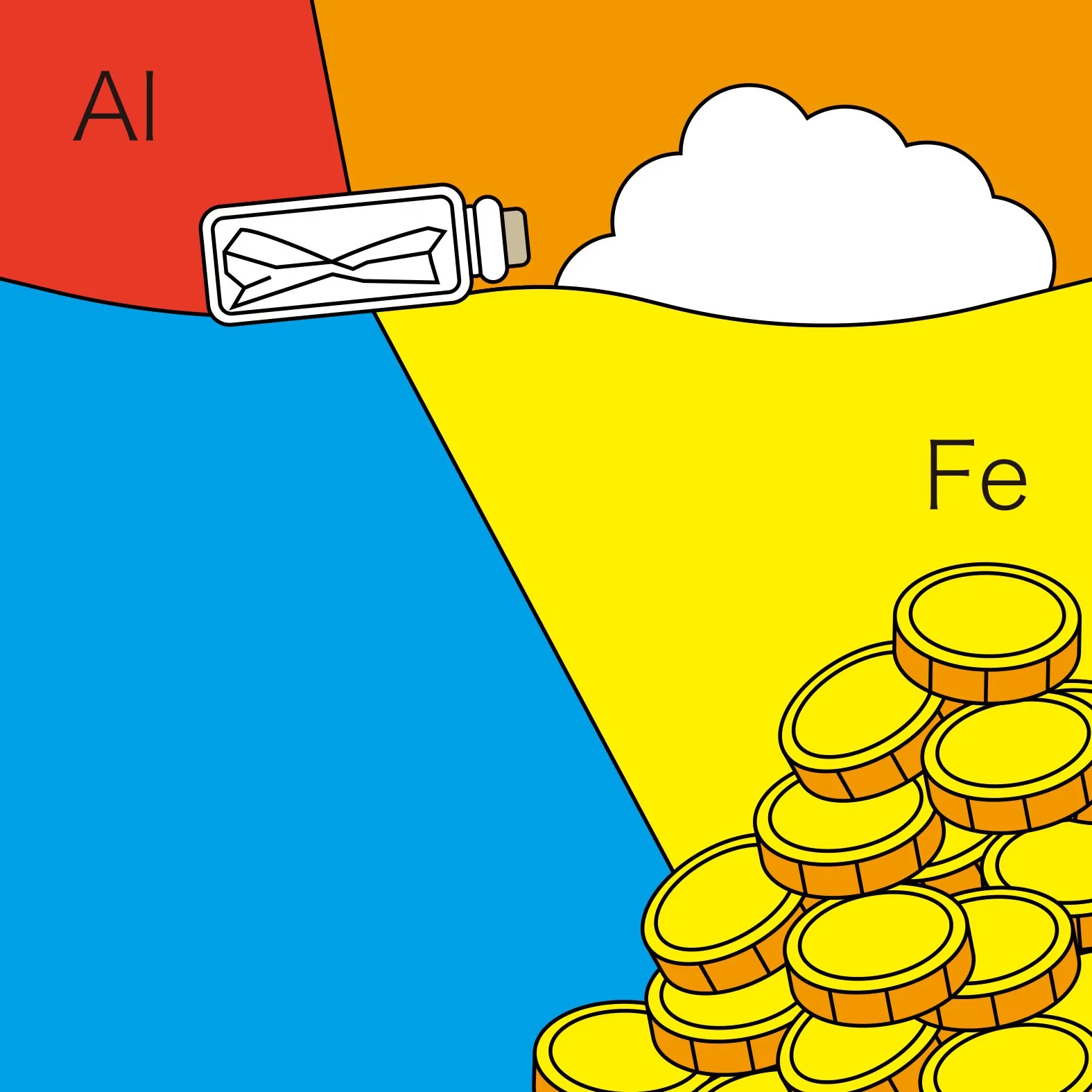鉄の3分の1という事実
アルミニウムの比重は、2.7。
比重とは、水を1としたときの相対的な重さ。 同じ体積で比べると、アルミニウムは水の2.7倍の質量があるということです。
では、他の金属と比べてみましょう。
| 金属 | 比重 | アルミを1としたとき |
|---|---|---|
| マグネシウム | 1.74 | 0.64(アルミより軽い) |
| アルミニウム | 2.7 | 1.00(基準) |
| チタン | 4.51 | 1.67 |
| 鉄 | 7.87 | 2.91 |
| 銅 | 8.96 | 3.32 |
| 鉛 | 11.34 | 4.20 |
アルミニウムは、鉄の約3分の1の重さ。
同じ大きさの部品を作るなら、アルミニウムは鉄の3分の1しか重さがない。
これが、アルミニウムが「軽い金属」と呼ばれる理由です。
なぜアルミニウムは軽いのか
「軽い」という現象には、原子レベルの理由があります。
原子量の違い
アルミニウム原子の原子量は、約27。
鉄原子の原子量は、約56。
アルミニウム原子は、鉄原子の約半分の重さしかない。
素材を構成する「部品」そのものが軽いのです。
原子の並び方
金属は、原子が規則正しく並んだ「結晶」でできています。
アルミニウムの結晶構造は「面心立方格子」。
鉄(常温)の結晶構造は「体心立方格子」。
どちらも原子が効率よく詰まった構造ですが、原子量の違いがそのまま密度(比重)の違いになります。
軽い原子が集まれば、軽い金属になる。
シンプルですが、これが本質です。
■ コラム:かつてアルミは「貴金属」だった
19世紀半ば、アルミニウムは金より高価でした。
アルミニウムは地殻中で最も豊富な金属元素ですが、 酸素と強く結びついているため、単体として取り出すのが極めて難しかった。
1886年にホール・エルー法(電気分解による精錬法)が発明されるまで、 アルミニウムは貴重品だったのです。
ナポレオン3世は、最も大切な客人にはアルミニウムの食器を、 それ以外の客には金や銀の食器を出したと言われています。
ワシントン記念塔(1884年完成)の頂上には、 当時最も貴重な金属としてアルミニウムが使われました。 重さはわずか2.8kg。当時の価格で銀の数倍だったそうです。
今では1円玉の素材として、誰もが手にする金属。
技術の進歩が、貴金属を日用品に変えました。
「軽い」と「薄くできる」は違う
ここで、重要な注意点があります。
「アルミは軽いから、薄くできる」とは限らない。
ヤング率(剛性)の問題
金属の「硬さ」には、いくつかの指標があります。
そのひとつが「ヤング率」(縦弾性係数)。
力をかけたときに、どれだけ変形しにくいかを示す数値です。
| 金属 | ヤング率(GPa) | アルミを1としたとき |
|---|---|---|
| アルミニウム | 70 | 1.00 |
| 鉄 | 210 | 3.00 |
| 銅 | 130 | 1.86 |
| チタン | 106 | 1.51 |
アルミニウムのヤング率は、鉄の3分の1。
同じ力をかけると、アルミニウムは鉄の3倍たわむ。
つまり、同じ厚さ・同じ形状で作ると、アルミニウムの部品は鉄より「たわみやすい」のです。
厚くするか、形状で補うか
剛性が必要な部品では、アルミニウムを使う場合、
- 厚くする:材料を増やして剛性を確保
- 形状を工夫する:リブ(補強の骨)を入れる、中空構造にする
といった設計が必要になります。
押出形材の強みは、ここにあります。
複雑な断面形状を一体で成形できるので、 材料を最小限に抑えながら、必要な剛性を確保できる。
軽さを活かすには、設計の工夫が必要。
これがアルミニウムの特性を理解する上で重要なポイントです。
熱膨張係数——もうひとつの注意点
アルミニウムは、温度変化で寸法が変わりやすい金属でもあります。
| 金属 | 線膨張係数(×10⁻⁶/℃) |
|---|---|
| アルミニウム | 23.1 |
| 銅 | 16.5 |
| 鉄 | 11.8 |
| ステンレス | 10〜17 |
アルミニウムの線膨張係数は、鉄の約2倍。
温度が上がると、鉄の2倍伸びる。
温度が下がると、鉄の2倍縮む。
高温環境や、温度変化が大きい環境で使う場合は、 この「伸び縮み」を考慮した設計が必要です。
例えば、長尺のアルミ形材を固定するとき、 すべての点を完全に固定すると、温度変化で歪みが生じることがあります。一部をスライド可能な固定にするなど、逃げを設ける設計が求められます。
■ コラム:新幹線の車体がアルミニウムである理由
新幹線の車体は、アルミニウム合金でできています。
0系(1964年〜)はスチール製でしたが、 300系(1992年〜)以降は、アルミニウム合金のダブルスキン構造が採用されました。
なぜかというと、軽くなれば、速くなる。
車体が軽いと、加速が良くなる。 車体が軽いと、ブレーキが効きやすくなる。
車体が軽いと、線路やモーターへの負担が減る。300系は、0系と比べて車両重量が約25%軽くなりました。
これが、最高速度270km/hを可能にした要因のひとつです。現在のN700Sでは、さらなる軽量化と剛性の両立のために、 中空のアルミ押出形材を溶接で組み合わせた構造が使われています。
形状で剛性を確保し、材料の軽さを活かす。
アルミニウムの特性を活かした設計の好例です。
合金による比重の違い
アルミニウム合金は、添加する元素によって比重が少し変わります。
| 合金系 | 主な添加元素 | 比重 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1000系 | 純アルミ | 2.71 | 電気伝導性◎、柔らかい |
| 2000系 | 銅(Cu) | 2.75〜2.85 | 高強度、航空機向け |
| 5000系 | マグネシウム(Mg) | 2.65〜2.70 | 耐食性◎、船舶・屋外 |
| 6000系 | Mg + Si | 2.70 | 押出性◎、汎用性高い |
| 7000系 | 亜鉛(Zn) | 2.75〜2.85 | 最高強度、航空機向け |
マグネシウムを含む5000系は、純アルミより少し軽い。 銅や亜鉛を含む2000系・7000系は、少し重くなる。
ただし、差は小さい(2.65〜2.85の範囲)。 どの合金でも「鉄の約3分の1」という軽さは変わりません。
「比重」を設計に活かす
設計者にとって、比重は実用的な数字です。
重量の概算
アルミニウム部品の重量は、簡単に計算できます。
体積(cm³)× 2.7 = 重量(g)
例えば、10cm × 10cm × 1cm の板なら、 100cm³ × 2.7 = 270g
鉄なら、 100cm³ × 7.87 = 787g
同じ形状で、約3分の1の重さになることがわかります。
押出形材の場合
押出形材は、断面積と長さで体積を計算します。
断面積(cm²)× 長さ(cm)× 2.7 = 重量(g)
複雑な断面でも、CADで断面積を出せば、すぐに重量がわかる。
■ コラム:飛行機の重量制限とアルミニウム
航空機の世界では、1kgの重量削減が大きな意味を持ちます。
機体が1kg軽くなると、その分だけ燃料を積めるか、貨物を積めるか、乗客を乗せられる。
長距離路線を飛ぶ大型機では、 1kgの軽量化が、機体寿命を通じて数十万円〜数百万円の燃料コスト削減につながる という試算もあります。
だから、航空機メーカーはグラム単位で軽量化を追求する。
ボーイング787では、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の採用が話題になりました。
しかし、機体の多くの部分は、今でもアルミニウム合金です。特に、アルミリチウム合金は、通常のアルミ合金より約10%軽い。
燃料タンクや貨物室の構造に使われています。「軽さ」が、そのまま経済価値になる世界。
アルミニウムの比重2.7は、航空機設計の出発点です。
まとめ
- 比重2.7:水を1としたとき、アルミニウムは2.7
- 鉄の約3分の1:同じ体積なら、アルミは鉄の3分の1の重さ
- 原子量が軽い:アルミ原子は鉄原子の約半分の重さ
- ヤング率は鉄の3分の1:同じ形状では、アルミは鉄よりたわみやすい
- 熱膨張係数は鉄の約2倍:温度変化で伸び縮みしやすい
- 合金による差は小さい:2.65〜2.85の範囲
軽さを活かすには
アルミニウムの比重2.7は、単なる数字ではありません。
鉄の3分の1という軽さは、設計の可能性を広げる特性です。
ただし、軽さだけを見て「鉄をアルミに置き換えればいい」とはなりません。
ヤング率が低いこと、熱膨張が大きいこと
—— これらの特性を理解した上で、形状や固定方法を工夫する必要があります。
押出形材は、その工夫を形にできる製法です。
中空構造、リブ構造、複雑な断面
—— 材料の軽さを活かしながら、必要な剛性を確保する。
軽さを「設計」で活かす。
それが、アルミニウムを使いこなすということです。
参考文献・データ出典
- 理科年表オフィシャルサイト(国立天文台編)https://official.rikanenpyo.jp/
- 一般社団法人 日本アルミニウム協会「アルミニウム材料の諸特性データベース:物理的性質」https://www.aluminum.or.jp/materialdb/3.html