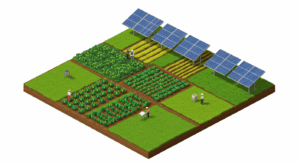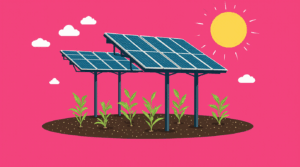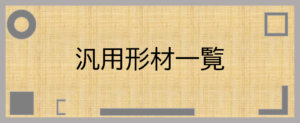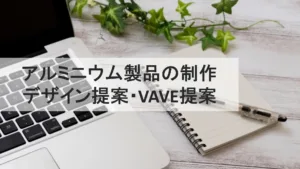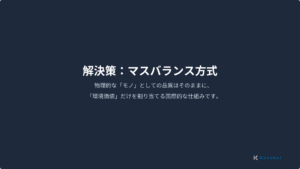「ソーラーシェアリングって、結局何がいいの?」
「20年間も電気を買い取ってくれるって本当?そのあとはどうなるの?」
「初期費用は高いんでしょう?元を取るのに一体何年かかるんだ…」
農業と発電を両立させる、ソーラーシェアリング。
興味はあるけれど、難しそうな言葉や仕組みが多く、一番肝心な「お金」の話、
そして「事業」としての実態は、よく分からない…と感じていませんか?
この記事では、そんな皆様の疑問に答えるため、ソーラーシェアリングの「儲けの仕組み」と、公的なデータを基にした「収支シミュレーションの参考例」、そして、この事業が直面する「リアルなリスク」まで、専門用語をなるべく使わずに、分かりやすく解説していきます。
Q1. そもそも、ソーラーシェアリングの「事業としてのメリット」とは?
はい、一番わかりやすいメリットは「農地の上で電気を作り、それをお金に変える仕組み」であることです。
しかし、その本質は、単なる金儲けの仕組みではありません。
農業を営む方にとって、「もう一つの、天候に左右されない安定した収入源を持つ、第二の事業」であるという点が最大の魅力です。
- 収入の柱が2本になる安心感: 農業収入が少ない月でも、売電収入が家計を支えてくれます。
- 未来への投資: 安定した収入があれば、新しい農業機械の購入や、後継者のための資金計画など、未来に向けた投資がしやすくなります。
- 電気代の削減: 作った電気を自分の農作業(ビニールハウスの暖房やポンプなど)に使えば、高騰する電気代を大幅に節約することも可能です。
このように、「農業を続けるための、力強いビジネスパートナー」となってくれるのが、
ソーラーシェアリングの本来の価値なのです。
Q2. どうして「20年間」も事業が安定するの? その後は?
これは「FIT(フィット)制度」という、国との非常に重要な約束があるからです。
事業を始めた年に決められた価格で、「20年間、電力会社が電気を買い取ることを国が保証します」という制度です。
国が長期保証をすることで、事業者は安心して銀行から融資を受けたり、設備投資をしたりできるわけです。
そして、20年後はどうなるの?
20年経つと、この保証期間は終了します(卒FITと呼ばれています)。
しかし、事業が終わるわけではありません。そこからは、
- 作った電気を自分の家や農作業で使い、電気代をほぼゼロにする(自家消費)
- 電力会社や新しい電気事業者に、その時々の市場価格で電気を売り続ける
- より高性能な最新パネルに交換して、さらに効率よく発電事業を続ける(リパワリング)
- 設備を撤去して、完全に農業だけの土地に戻す
など、「作った電気をどう使うか、一番得な方法を自分で選べる新しい経営ステージ」が始まります。
Q3.【本題】架台選びが、20年間の事業収支をどう変えるのか?(試算例)
「で、結局いくらかかるの?」という疑問にお答えするため、ここでは、公的データを基にした試算例(モデルケース)として、具体的な数字を挙げて比較してみます。
《設定モデル》
- 畑の面積: 約10アール (1,000㎡)
- 設置する設備: 50kWのソーラーシェアリング設備
- 年間発電量(予測): 約58,400 kWh
- 年間売電収入(予測): 58,400 kWh × 9.2円 = 約53.7万円
データソース:NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)「日射量データベース」の愛知県データと、JPEA(太陽光発電協会)が示す標準的な設備利用率13.4%を基に、2024年度FIT価格9.2円/kWhで算出。
この収入は、ソーラーパネルの発電量で変化するため、架台がアルミでも鉄でも変わりません。
差がつくのは、事業の「始まり」と「終わり」にかかるコストです。
【比較表①】初期費用(部材費+工事費)の試算例
ソーラーシェアリングの初期費用は、大きく「①電気設備費(パネル、パワコン等)」と「②架台+工事費」に分けられます。
ここでは、業界で一般的と言われる総額約850万円を基準に、架台の違いがどう影響するかを見ていきます。
| 費用の種類 | 従来のスチール製架台 | アルミ架台 |
| ①電気設備費 | 約550万円 | 約550万円 |
| ②架台+工事費 | 約300万円 | 約230万円 |
| 初期費用の合計(試算) | 約850万円 | 約780万円 |
なぜ「架台+工事費」に差が出るのか?
上の表の「②架台+工事費」に、なぜこれほどの差が生まれる可能性があるのでしょうか。
その内訳を、「部材費」と「工事費」に分けて見ていきましょう。
1. 部材費のからくり
「単価」は高いが、「総額」は安くなる可能性
まず、材料1kgあたりの価格(単価)だけを見ると、アルミは鉄よりも高価です。
- 鉄鋼製品(メッキ処理・加工後): 約300~450円/kg
- アルミ形材(押出・加工後): 約650~750円/kg
「じゃあ、やっぱりアルミの方が高いじゃないか」と思いますよね。
しかし、ここが重要なポイントです。
アルミは、鉄の約3分の1の重さ(比重)しかありません。
同じ強度を持つ架台を作るために必要な材料の重さを比べると、
- 鉄製架台に必要な重さ(推定): 約8,000 kg (8トン)
- アルミ製架台に必要な重さ(推定): 約3,000 kg (3トン)
となります。これを基に、架台全体の材料費を計算してみると…
- 鉄製架台の材料費: 8,000kg × 400円/kg = 約320万円
- アルミ製架台の材料費: 3,000kg × 700円/kg = 約210万円
つまり、こういう事です。
2. 工事費の大幅な削減効果
さらに、この「軽さ」は工事費にも劇的な影響を与えます。
- 運搬費: 重い鉄の運搬には大型トラックが必要ですが、アルミなら小型トラックで済みます。
- 施工費: 鉄の設置には大型クレーンと多くの作業員が必要ですが、アルミなら重機をほとんど使わず、少人数で組み立てが可能です。
- 基礎工事費: 架台全体が軽いため、地面にかかる負荷も減り、基礎工事を簡略化・低コスト化できます。
これらの要素を総合すると、私たちが前の表でお示しした「架台+工事費」で70万円程度の差が生まれるという試算は、十分に現実的なものとしてご理解いただけるかと思います。
【比較表②】撤去費用(20年後)の試算例
次に、事業終了時の撤去です。
2024年の新ルールから、この撤去費用を事前に準備しておくことが義務化されました。
だからこそ、この費用がいくらになるかは、これまで以上に重要な問題です。
《現在のスクラップ買取価格(2025年7月時点の参考相場)》
- 中古ソーラーパネル: 状態によるが、1枚1,000円~3,000円程度で取引される例も。
- 鉄スクラップ(H2): 約40~50円/kg
- アルミサッシ(ガラ): 約200~230円/kg
この現在の相場を基に、50kW設備の撤去にかかる費用と収益を、より具体的に分解してみましょう。
| 費用の種類 | 従来のスチール製架台 | アルミ架台 | 解説 |
| 1. パネル・電気設備の撤去 | 約30万円 | 約30万円 | パネル(約120枚)やパワコン、配線を取り外す作業費です。これはどちらの架台でも共通でかかります。 |
| 2. 架台の解体作業費 | 専門業者必須:約60万円 | 専門業者依頼:約35万円 | 鉄の場合: 20年の雨風でサビついたボルトや溶接箇所を切断する必要があり、危険な「破壊作業」となります。 アルミの場合: サビによる固着がほぼなく、スムーズに分解可能。DIYも物理的には可能ですが、安全を考慮し専門業者に依頼した場合でも、作業が容易なため鉄より安価になります。 |
| 3. 重機・運搬費 | クレーン・大型トラック:約20万円 | 軽トラックで十分:約5万円 | 鉄の運搬には重機と大型車が必須。アルミは軽量なため、運搬費も大幅に抑えられます。 |
| 4. 廃棄物処理費 | 産廃として処分:約10万円 | ほぼ発生しない | 鉄はサビや劣化した塗装部分が、産業廃棄物として処分費用がかかる可能性があります。アルミはほぼ100%が有価物としてリサイクルされます。 |
| 小計(かかる費用) | 約120万円 | 約70万円 | 撤去にかかる費用だけで、約50万円もの差が生まれます可能性があります。 |
| 5. リサイクル・リユース売却益 | 約50万円 (鉄 36万 + パネル 14万) | 約78.5万円 (アルミ 64.5万 + パネル 14万) | 架台の差: 鉄(8t×45円)に対し、アルミ(3t×215円)は資源価値が圧倒的に高いです。 パネルの差: 20年後のパネルも発電能力は残っており、中古市場で売却できる可能性があります。(120枚×約1,200円で試算) |
| 最終的な収支(見込み) | 50万円 – 120万円 = -70万円(負担) | 78.5万円 – 70万円 = +8.5万円(利益) | 鉄は大きな「負債」となる一方、アルミは売却益で費用をまかない、「利益」が生まれる可能性すらあるのです。 |
データソース:一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)「太陽光発電事業の終了に向けた計画的準備の必要性」および、日本金属リサイクル工業会が公表するスクラップ価格等を参考。
投資対効果の考え方
この、より現実的な費用で、費用回収期間を再計算してみましょう。
- アルミ架台の場合: (初期費用780万円 - 将来の売却益8.5万円) ÷ 年間収入54万円 = 約14.2年
- 従来のスチール製架台の場合: (初期費用850万円 + 将来の撤去費用70万円) ÷ 年間収入54万円 = 約17.0年
「初期投資を抑え、回収を早め、最後の出口(撤去)のリスクまで最小化する」 これが、私たちのアルミ架台が提供できる、20年間の事業を通した最大の価値なのです。
【補足コラム】中古ソーラーパネル市場の「真実」
「20年後、本当にパネルなんて売れるの?」
「みんなが一斉に売りに出したら、価値が暴落するんじゃない?」
そのご指摘は、まさにその通りです。これは「2030年問題」として、業界でも課題となっています。
2012年から始まったFIT制度の設備が一斉に20年後を迎えるため、
中古パネルの供給が急増し、価格が今より下がる可能性は高いと考えるのが現実的です。
しかし、「価値がゼロになる」「産廃として費用を払って捨てる」というリスクは極めて低いと考えられます。なぜなら、価格の下落圧力と同時に、中古パネルを受け入れる「市場の拡大」も進んでいるからです。
- リユース市場の成熟: 性能をきちんと検査し、品質を保証して販売する専門業者が増えています。
- 海外需要の拡大: 日本の高品質な中古パネルは、安価で信頼性が高いため、特に発展途上国で非常に高い需要があります。
- 国内の新たな需要: 災害時の非常用電源や、電気自動車(EV)の充電用など、新しい使い道も生まれています。
この記事のシミュレーションでお示しした「中古パネルの売却益」という数字は、将来を約束するものではありません。しかし、重要なのは金額そのものではなく、
「20年後、あなたのソーラーパネルは、お金を払って捨てる“産業廃棄物”ではなく、誰かが欲しがる“価値ある資産”であり続ける可能性が極めて高い」
という事実です。
Q4.【最大のリスク】許可更新ができず、事業が続けられなくなったら?
2024年の新ルールで、これが最も現実的なリスクとなりました。
もし、3年または10年後の更新審査の際に、「営農が適切に行われていない」と判断された場合、どうなるのか。
これは、単にFITのルールから外れる、という単純な話ではありません。
- ステップ①:「農地の一時転用許可」が取り消される
- ステップ②:「原状回復命令」が出される(設備の全撤去命令)
- ステップ③:FITの「事業計画認定」が取り消される
このリスクを理解することが、事業を成功させる上で何よりも重要になります。
Q5.事業計画の前に:知っておくべき公的ルールとリスク管理
20年にわたるソーラーシェアリング事業は、大きな投資です。
その投資を守り、収益性を正確に判断するためには、国の公式ルールを理解し、様々なリスクに備えることが不可欠です.
ここでは、事業計画を立てる上で最低限知っておくべき、公的なルールとリスク管理のポイントをまとめました。
■補助金の活用について
国や地方自治体は、再生可能エネルギーや農業振興を目的とした補助金・交付金制度を設けている場合があります。
- 注意点①:申請は「事業開始前」が鉄則
補助金の多くは、工事の契約や着工前に申請することが絶対条件です。
順序を間違えると対象外となるため、計画の早い段階で情報を集める必要があります。 - 注意点②:制度は常に変わる
補助金は、年度や地域によって内容が大きく異なり、公募期間も非常に短いことがほとんどです。
去年あったものが、今年はない、ということも珍しくありません。 - 注意点③:多様な制度の存在
一般的な設備の導入補助のほか、例えばFIT制度を利用しない自家消費型の設備に特化した補助金など、目的によって様々な制度が存在します。
ご自身の計画に合った制度があるか、まずは地域の市町村や農業委員会に問い合わせるなど、徹底的に調べることが重要です。
■万が一の備え(保険加入)について
事業期間中には、台風などの自然災害、設備の盗難や破損といった、予期せぬ事故が起こる可能性があります。
- 損害保険への加入 こうしたリスクに備え、設備の修繕費用などをカバーする損害保険への加入を強くお勧めします。これは任意ですが、安定した事業運営のためには重要なリスク管理の一環です。
- 設備による違い 保険料や補償内容は、設備の構造によっても変わる可能性があります。例えば、軽量で部分的な修理がしやすいアルミ製架台のような設備は、修繕コストの面で有利に働く場合もあります。どのような保険が最適か、複数の保険会社に見積もりを取って比較検討することが賢明です。
まとめ:最初の選択が、20年間の事業の成否を分ける
ソーラーシェアリングが、農業経営を安定させる力強い事業であることは間違いありません。
しかし、その効果を最大限に引き出すためには、「どの設備を選ぶか」という経営判断が非常に重要になります。
この記事でお示しした数字は、あくまで公的データに基づいた「参考例」です。
実際の費用や収支は、あなたの農地の場所、広さ、地盤の状態、そして何より、どのような農業を営むかによって大きく変わります。
だからこそ、私たちは「あなたの農地」に合わせた、オーダーメイドの正確な個別見積もりが不可欠だと考えています。
「うちの畑なら、実際どうなんだろう?」
「もっと詳しく話を聞いてみたい」
そう思われましたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
無理な営業は一切いたしません。
あなたの農業の未来を、一緒に真剣に考えさせていただければ幸いです。
参考資料:営農型太陽光発電のルールについて
営農型太陽光発電は、国が定めるルールに基づいて行われます。
ここでは、制度の変遷と、参考となる公式資料の概要をまとめました。
ソーラーシェアリング新旧比較表(簡易版)
| 項目 | 旧制度 (~2024年3月) | 新ガイドライン (2024年4月~) | ポイント |
| 報告義務 | 毎年の報告を求めるが、書式や内容は不明確な場合も。 | 栽培実績に加え、収支報告書の毎年の提出を義務化。 | 営農・経営実態の継続的なモニタリングが厳格化。 |
| 撤去費用 | 明確な規定なし。 | 申請時に撤去費用負担の証明書提出を義務化。 | 事業終了時の原状回復の確実性を担保するセーフティネット。 |
| 最低地上高 | 明確な規定なし。 | 原則として2メートル以上を確保。 | 農業機械の利用効率を保証し、営農継続を本気で求める姿勢。 |
| 地域合意形成 | 個別案件ごとの判断。 | 「地域計画」との連携、協議の場での合意が要件化。 | 事業の計画段階から地域との調和が必須に。 |
■これまでの経緯(簡単な年表)
制度の歴史を知ることで、現在のルールがなぜ厳しくなったのか、その背景を理解できます。
営農を続けながら太陽光発電を行うための、最初の公式ルール(通知)が国から出されました 。
ルールが改定。特に、地域の農業を担う「担い手」や、荒廃農地を再生利用する場合に、一時転用許可の期間が従来の3年から10年に延長されました 。
※注意点:この「10年許可」は誰でも受けられるわけではなく、特定の条件を満たす場合に限られます 。
これまでの通知が廃止され、より厳格な新しい「ガイドライン」が制定されました 。
背景:発電ばかりを優先し、農業がおろそかになる事例が増えたためです 。
主な変更点
- 毎年の収支報告が義務化
- 設備の撤去費用を確保していることの証明が必須に
- 架台の高さは原則2m以上を確保
※重要なポイント:この新しいルールは、これから始める人だけでなく、既に設備を設置している人も、次の許可更新のタイミングで適用されます 。
■公式資料の概要
より詳細な情報は、以下の国の公式資料で確認できます。
1.ガイドライン
「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」の制定について
令和7年3月 31 日 6農振第 2983 号
参考資料:農林水産省pdf
どんな資料?: 制度全体の基本ルールブックです。
書かれていること:農地転用許可を得るための基準、必要な申請書類、
守るべき条件などが網羅的に定められています 。制度の根幹となる最も重要な公式文書です。
2.事業者向けQ&A
令和7年4月(改訂版)
参考資料:農林水産省pdf
どんな資料?:事業者(農家や発電事業者)向けの公式解説書です。
書かれていること:ガイドラインの内容について、事業を行う側が抱く「こんな時はどうするの?」という具体的な疑問に、一問一答形式で分かりやすく答えています 。例えば、「どこに相談すればいいか」「どんな書類を準備すればいいか」といった実務的な内容が中心です。
3.行政担当者向けQ&A
営農型太陽光発電の実務用Q&A(都道府県、市町村及び農業委員会担当者向け)
令和7年4月(改訂版)
参考資料:農林水産省pdf
どんな資料?:行政(都道府県や市町村、農業委員会)向けの公式解説書です。
書かれていること:申請を「審査・指導する側」が、どのように許可の判断を下し、事業者への指導を行うべきかが書かれています 。事業者がこの資料を読むと、「行政がどこをチェックしているのか」という裏側を知ることができます。
ソーラーシェアリングを、より詳しく知りたい方へ
あなたの立場に合わせた、情報をご用意しております。