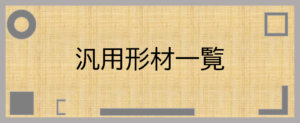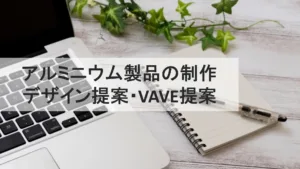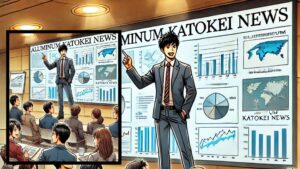長く製造業に関わってきた人ほど、「言われたことをきちんとやる」ことが仕事の基本だと感じてきたかもしれません。
それは決して間違いではありませんが、「気づいたことを自分から提案する」ような動き方がしにくい空気もあったのではないでしょうか。
たとえば、作業の中で不便を感じたときに「こうしたら良くなるのでは?」と思っても、それをどこに伝えればいいのか分からない。
あるいは、伝えたとしても「そんなの今はいいよ」と受け流されてしまう、または否定され傷ついたこともあるでしょう。
加藤軽金属工業では、そういった声や気づきを実行に移すための仕組みとして、プロジェクト制度を導入しています。
出発点にあるのは、「こうした方が良くなる」という社員一人ひとりの実感や想い。
上からの指示ではなく、自らの意思で動き出すことを支える制度です。
プロジェクト制度のしくみと考え方
このプロジェクト制度は、「やってみたい」と思った社員が自由に動き出せる枠組みです。
テーマは決まっていません。身の回りの改善から全社的な仕組みまで、提案する人の視点と気づきによって内容が決まります。
発案者がそのままリーダーとなることもあれば、仲間に声をかけて進めるケースもあります。
誰を巻き込むかも自由で、同じ部署の仲間でも、別の部署のメンバーでも構いません。
上司や管理職の関わり方も柔軟です。
必要に応じて相談を受けたり、状況を共有したりしますが、あくまで主体は発案者自身。
ルールよりも動機、形式よりも行動を大切にしています。
ただし、制度の信頼性を支える運用の仕組みも整えられています。
プロジェクトには管理者が付き、進捗や行動の履歴が記録・可視化されます。
「どのようなテーマで、誰が関わり、どこまで進んでいるか」がプロジェクト単位で整理されているのです。
現場での広がりと実際
実際に動き出したプロジェクトは、内容も規模もさまざまです。
備品の配置を見直す、作業手順を整理する、掲示物や社内ツールの改善など、どれも日常の気づきから生まれた取り組みです。
共通しているのは、「誰かが困っていたこと」「ずっと気になっていたこと」が出発点になっていること。
課題の大小を問わず、動きの中心には“やってみたい”という意思があります。
部署を超えてメンバーが集まるプロジェクトも少なくありません。
ふだん関わりの少ない人同士が、テーマを通じて協力し合うことで、新しいつながりや発見が生まれています。
また、制度の存在によって、「言いづらい」「出しづらい」と感じていたテーマも正面から取り上げられるようになりました。
プロジェクトとして承認されれば、発案者は正式にリーダーとなり、自分の言葉に責任を持って動くことになります。
上からでも、下からでもない。自らの行動が、会社の空気を少しずつ変えていくのです。
ミッション・ビジョン・バリューとの関わり
この制度の中で起きている行動には、私たちが大切にしている考え方が自然とにじんでいます。
自ら動くこと。協力し合うこと。遠慮せずに対話し、前に進めること。
こうした振る舞いの中に、ミッション・ビジョン・バリューのエッセンスがさりげなく表れていると感じています。
→ 当社のミッション・ビジョン・バリューについてはこちらをご覧ください。
おわりに
制度ができたことで、「気になっていたけれど動けなかったこと」が、少しずつ動き出しました。
「自分がやる」と声を上げた人がリーダーとなり、責任を持って進めていく。
それは、ただの意見ではなく、行動として形にしていく意思です。
プロジェクトは、内容・進み方ともに記録され、きちんと制度として扱われます。
取り組みは個人や部署の評価に反映され、成果が認められた場合には報酬にもつながる仕組みとなっています。
やらされるのではなく、自らやる。
その姿勢が見られ、伝わり、きちんと認められる。
プロジェクト制度は、動いた人が報われる制度です。
現場で始まった一つひとつの動きが、会社のあり方を少しずつ変えていきます。
これは、改善だけを目的とした制度ではありません。
一人ひとりが、会社の一部を担うための仕組みです。